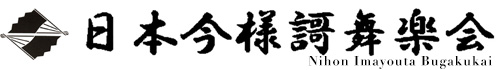日本今様謌舞楽会の
公式ホームページです。
今様とは平安時代に流行した歌曲の事です。
当世風・今風であったことから今様と呼ばれ、身分の上下を問わず広く流行しました。
『遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん』で始まる歌曲は、皆様も一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。この歌曲は、今様を愛好していた後白河法皇 編纂の梁塵秘抄に掲載されており、この他にも梁塵秘抄の一部は現代まで伝わっています。そして、今様の流行には 源義経の恋人であった静御前、平清盛の祇王祇女、仏御前などよく知られる『白拍子』等の女性芸能者が大きな役割を担いました。
日本今様謌舞楽会では 今様の研究、国内外での今様の奉納・公演、又1986年に今様合を復興させ、その実演等の活動を行っております。
②.jpg)
2025年(令和7年)活動記録

.jpg)
今様合復興40周年記念
今様合復興40周年記念特設ページはこちら
◆令和1月26日(日)午前11時〜
無事に終了いたしました
第1回今様合 賀茂別雷神社(上賀茂神社)【本殿】にて
詠題『記録』
◆ 令和7年3月23日(日)午後4時〜
無事に終了いたしました
第2回今様合 賀茂御祖神社(下鴨神社)【祈祷所[鴨社禮殿]】にて
◆令和7年4月5日(土)午後2時〜
無事に終了いたしました
第3回今様合 石清水八幡宮
◆令和7年4月6日(日)午後4時15分〜
無事に終了いたしました
第4回今様合 八坂神社
◆令和7年4月26日(土)午前11時〜
無事に終了いたしました
第5回今様合 永観堂
◆令和7年4月27日(日)午後6時30分〜7時30分頃
無事に終了いたしました
第6回今様合 東寺(金堂南側予定)
※ライトアップ期間中の入場料1,000円
◆令和7年5月10日(土)午前11時予定〜
無事に終了いたしました
第7回今様合 長岡天満宮
◆令和7年5月31日(土)午後2時〜
無事に終了いたしました
第8回今様合 寂光院
◆令和7年6月1日(日)午後2時〜
無事に終了いたしました
第9回今様合 城南宮
◆令和7年6月7日(土)午後1時30分〜
無事に終了いたしました
第10回今様合 新日吉神宮
◆令和7年6月30日(月)午後2時〜
無事に終了いたしました
第11回今様合 生身天満宮
◆令和7年8月4日(月)午後2時〜
無事に終了いたしました
第12回今様合 熊野本宮大社
◆令和7年8月5日(火)午前11時〜
無事に終了いたしました
第13回今様合 熊野速球大社
◆令和7年8月5日(火)午後1時半〜
無事に終了いたしました
第14回今様合 熊野那智大社
◆令和7年10月12日(日)午後3時〜
無事に終了いたしました
第15回今様合 法住寺
「第40回今様合の会」
お知らせ
◆ 令和7年10月12日(日)午後3時〜
法住寺 阿弥陀堂・後白河法皇ご宝前にて
第40回『今様合の会』
◆令和7年11月3日(月・祝)午後4時30分〜
※ご予約制
法住寺 にて
『葉菊の饗宴(はぎくのうたげ)』
◆令和7年11月第二日曜日
今様とは
今様
imayo

今様は今からおよそ800有余年前京の都に大変流行致しました。神楽、催馬楽、田楽等に続いて当時大変今風だったところから「今様」と呼ばれるようになりました。 時の後白河院は世にもまれな今様の熱愛家であられたことは有名です。また梁塵秘抄を集大成されたことは歴史上有名であります
白拍子
shirabyoshi

白拍子の起源は『平家物語』「祇王」の段に「白拍子のはじまりけることは、むかし鳥羽院の御宇に島の千歳・和歌の舞とて、これら二人が舞ひ出したりけるなり」とあり、鳥羽院の時代としています。服装については、当初、水干に立烏帽子、白鞘巻の太刀を差して舞っていましたが、のちに烏帽子・太刀を除き、水干だけ身につけた、と説明されています。
白拍子の語義は、本来、「歌につけて打つ拍子のこと」、あるいは「管弦の伴奏なしで歌うこと」などを意味したとされますが、転じて その歌舞を行う人自身を指すようになったと考えられます。その芸能の形態は『平家物語』によれば、今様や朗詠を歌った後に、鼓などを伴奏に舞ったとされます。
今様合とは
今様合(いまようあわせ)は、平安時代の後期、特に院政期に盛んに行われた歌謡の優劣を競う遊びです。「今様」とは、当時の流行歌謡を指し、七五調四句の形式で、独特の節回しが特徴でした。
院政期は、退位した天皇が政治の実権を握る時代で、宮廷文化に新たな潮流が生まれていました。後白河法皇は、今様に非常に熱心で、自らも歌い、その普及に大きく貢献しました。貴族社会では、歌や芸能に対する関心が高まり、「物合」という優劣を競う遊びが流行し、その一つとして今様合が行われました。

今様合は、歌合と同様の形式で行われ、参加者は左右に分かれて今様を歌い、その優劣を競いました。歌唱力や表現力が評価のポイントとなり、扇や鼓などの楽器を使うこともありました。判者が優劣を判定し、勝敗を記録する役職も存在しました。また、今様合は単なる遊びにとどまらず、当時の文化や芸能に大きな影響を与えました。今様の流行は、新しい歌謡の形を追求し、後の日本の歌謡の基礎となりました。また、白拍子たちの歌舞は、今様の魅力をさらに高め、能や狂言などの芸能にも影響を与えたと言われています。